支援員必見!服薬ミス事例5選と原因・防止の工夫
支援員として日々欠かせない業務のひとつが「服薬支援」です。
利用者さんの健康や生活の安定に直結する大切な業務でありながら、支援現場では服薬に関するヒヤリ・ハットや実際のミスがどうしても起こってしまいます。
「薬は飲んだと思ったけど、実は吐き出していた」
「双子だから似ていて薬を取り違えてしまった」
「頓服の間隔を守らずに投与してしまった」
現場で起きた服薬ミスを振り返ることは、支援員にとって自分の仕事を見直す大きな学びになります。今回は、実際にあった服薬ミスの事例5選を紹介し、その原因と防止策を考えていきます。

1.薬の取り違え事件
薬の取り違えは、現場で最も多いミスのひとつです。利用者さんの人数が多い施設では、朝食後や夕食後などに一度に複数人の薬を準備する場面が多く、その分リスクも高まります。
事例①:双子の兄弟の薬を取り違え
朝食後の服薬支援中、パート職員Yさんが双子の兄に弟の薬を渡してしまいました。外見も似ているため「兄に弟の薬を飲ませてしまった」と気づかずに服薬させてしまいました。
幸い、兄が必要としていた薬の一部が飲めなかっただけで大きな健康被害は出ませんでしたが、もし逆のケースであれば重篤な副作用を招いた可能性もありました。
事例②:二人分の薬をまとめて準備
職員がAさん・Bさんの薬を同時に準備し、投薬の際にAさんへBさんの薬を渡してしまいそうになりました。偶然、文字が読めるAさんが「これ、自分のじゃないよね?」と気づいたことで大事には至りませんでした。
原因
- ラベルの確認不足
- 外見が似ている利用者(双子など)の取り違え
- 複数人分を一度に準備する作業方法
防止策
- 薬袋の名前を声に出して読み上げながらダブルチェック
- 投薬は必ず一人ずつ、順番に行う
- 本人確認(声かけ)を服薬時のルールとして習慣化
2.薬を飲んだかどうかの確認漏れ
服薬支援でよくあるのが「飲んだと思っていたけれど、実は飲んでいなかった」というケースです。利用者さんによっては薬を嫌がる方や、口に入れても飲み込まず吐き出してしまう方もいます。
事例①:吐き出してしまったケース
Cさんは口に薬を入れたものの、実際には飲み込まずにそっと吐き出してしまいました。支援員は「飲んだ」と思い込み、服薬記録に「済」と記載。しかし、片付けの際に薬がトレーに残っていたことから発覚しました。
事例②:多量の薬での飲み残し
Dさんは7錠の薬を一度に渡され、自分で服薬しました。支援員はその場を離れ「飲んだ」と記録。しかし片付けの際、床に1錠落ちているのを別の職員が発見しました。
事例③:二重投与のヒヤリ
Eさんの薬を投与した後、チェックの記録がされていなかったため、別の職員が「まだ投与されていない」と勘違いし再度投薬。結果的に二重投与となってしまいました。幸い健康被害は出ませんでしたが、大きな事故につながる危険な事例です。
原因
- 「飲み込んだ」という確認不足
- 忙しさによる思い込み
- 投薬チェック欄の記入漏れやごみの廃棄忘れ
防止策
- 必ず口腔内を確認し、飲み終えるまで目を離さない
- 薬の量が多い方はスプーンで小分けにして渡す
- チェック欄への記入は「その場で」必ず行う(後回しにしない)
3.投薬時間の間違い
薬には「食前」「食後」「就寝前」など投薬時間の指定があります。忙しい現場ではこの時間を取り違えてしまうことがあり、利用者さんの体調に直接影響します。
事例①:食前投薬を忘れたケース
ショート利用のDさんは、食前30分に投薬が必要でした。しかし支援員が失念し、食堂に誘導して食事介助を始めてしまいました。別の職員が薬箱に薬が残っていることに気づき、慌てて投与。その後の食事時間に影響が出てしまいました。
事例②:眠剤を夕食前に投与
Eさんに眠剤を誤って夕食前に投与してしまい、食事中に強い眠気が出て食事摂取が困難になってしまいました。
原因
- 申し送り不足
- 服薬時間の勘違い
- スケジュール表の確認不足
防止策
- 投薬時間を大きく表示したスケジュール表を準備
- 投薬前に必ず声に出して確認する習慣
- 二人以上でのクロスチェックを徹底
4.薬の飲み忘れ
「飲ませたつもり」「飲んだだろう」という思い込みが原因で起こるのが薬の飲み忘れです。特に自立度が高い方の場合、支援員が気づきにくいこともあります。
事例:自立度の高いFさんの飲み忘れ
Fさんは食事やトイレを一人でこなせる方でした。食後にトレーを戻した後、そのまま居室へ戻ってしまい、薬を飲まずに1時間が経過。支援員は他の利用者の介助に追われ、すぐに気づくことができませんでした。
原因
- 繁忙による見落とし
- 記録と実施の時間差
防止策
- 食後の薬を「食事支援の流れの一部」と位置づける
- トレー返却時に必ず「薬は飲みましたか?」と声かけ
- 自立度が高い方こそ丁寧にチェックする意識
5.頓服薬の誤投与
頓服薬は「必要時のみ」使用される薬です。通常薬と比べると管理が難しく、誤投与のリスクも高まります。
事例①:毎食後と勘違いして投与
Gさんは発作時のみ頓服薬を使用するはずでしたが、職員が「毎食後に必要」と勘違いして3日連続で投与してしまいました。
事例②:短時間での重複投与
ショート利用のHさんが不穏な状態で、22時に頓服を投与。しかし改善しなかったため、支援員は24時に再度投与。その後、家庭からの連絡帳に「4時間は間隔を空けて投与」と記載されていたことに気づきました。
原因
- マニュアルや記録の未確認
- 申し送り不足
- 「頓服薬=使ってよい薬」という誤解
防止策
- 頓服薬は通常薬と別ケースに保管
- 投与理由・投与時間を必ず記録する
- 家族や医師の指示内容を常に確認

まとめ|服薬ミスを防ぐために支援員ができること
服薬支援は、支援員にとって「一番基本で一番大切な業務」です。
しかし、日常の中では「慣れ」や「忙しさ」から確認が甘くなり、ミスにつながります。
服薬ミスを防ぐためには、次のような意識と工夫が欠かせません。
- ダブルチェックを徹底する
- 声かけを欠かさない
- 記録をその場で残す
- 本人確認を習慣化する
これらの小さな積み重ねが、利用者さんの健康と安心を守ります。
支援員一人ひとりの意識が変わることで、施設全体の安全も高まります。
「大丈夫だろう」ではなく「必ず確認する」という姿勢を忘れないようにしましょう。
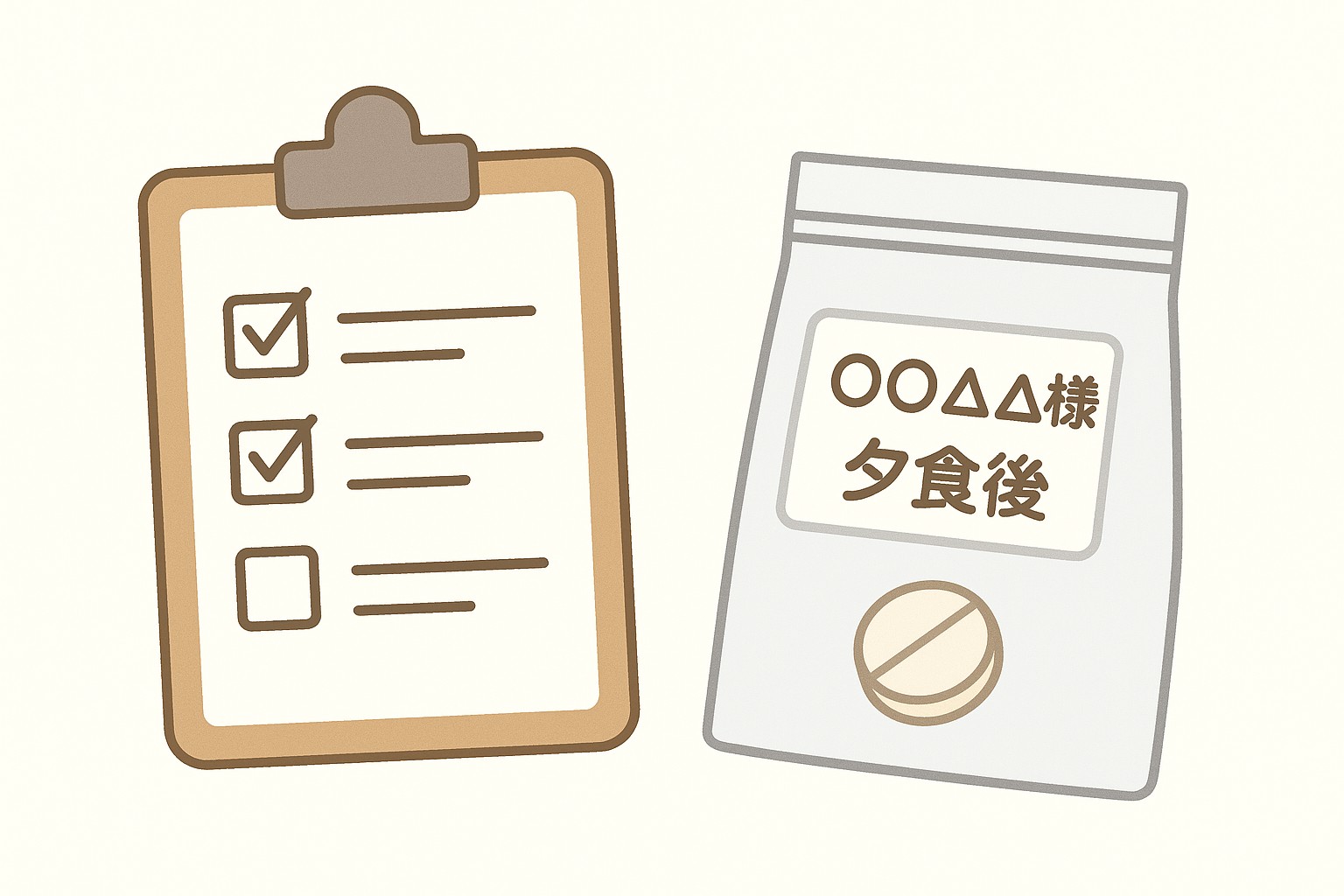


コメント